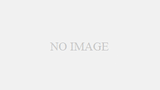相続が10年以内に連続して起きた場合で、最初の相続の際に相続税を支払っているときには、2回目の相続の際に発生する相続税を減額(相次相続控除)できることがあります。今回はその制度である相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)について見ていきたいと思います。
目次
1.相続税を減額できるケースの確認
2.減額できる人
上記のケースで見てみると、今回亡くなったお父さん(被相続人)の相続により、財産を得た相続人である息子が減額できる人となります。ここでのポイントは相続人であるということです。相続人でない場合は減額することはできません。
3.減額できる金額
減額できる金額を以下の事例により計算してみます。
①今回亡くなったお父さん(被相続人)が4年前(1年未満の端数は切捨て)に、相続人として、相続税を100万円支払った。そのときの純相続財産は5000万円。
※純相続財産=相続財産ー債務・葬式費用
②今回亡くなったお父さんの純相続財産は6000万円。
③相続人である子供は2名で相続した上記の純相続財産はそれぞれ2500万円、3500万円。
④相続人である子供の相続税はそれぞれ200万円、300万円。
手順1)100万円×0.6(10年△4年=6年)=60万円
前回の相続によりお父さんが納付した相続税100万円は1年ごとに10%減額し、10年後にはゼロとなります。つまり、1年ごとに10万円減額します。今回は4年経過しているため、40%減額し、60万円となります。この金額が減額できる最大額となります。
手順2)今回の純相続財産6000万円÷4900万円(前回の純相続財産5000万円-前回の相続税100万円)=1.224…>1 ∴1
1より大きい場合は1とします。前回の純相続財産より今回の純相続財産が大きい場合は1となります。今回のケースは1より大きくなるため、1として計算します。
※1より小さい数字の場合は、その数字を使います。たとえば前回の純相続財産から前回の相続税を差し引いた金額が5000万円、今回の純相続財産が2000万円の場合は、2000万円÷5000万円=0.4となります。この算式の意味は、前回の純相続財産に対する今回の純相続財産の割合を計算しており、1より大きい場合は1としています。
手順3)60万円×1=60万円(手順1×手順2)
手順4)60万円×2500万円÷6000万円(2500万円+3500万円)=25万円 純相続財産2500万円を得た相続人の減少する相続税額
手順5)60万円×3500万円÷6000万円(2500万円+3500万円)=35万円 純相続財産3500万円を得た相続人の減少する相続税額
上記のとおり、純相続財産2500万円の財産を得た相続人は25万円相続税が減額し、純相続財産3500万円の財産を得た相続人は35万円の相続税が減額します。手順4と5は、手順3で計算した減額できる相続税を各相続人に割り振る計算をしています。
4.まとめ
今回は10年以内に連続して相続が発生した場合に相続税が減額できる制度を見てきました。最初の相続の際に相続税を支払っている場合には、今回の相続税が減額できる可能性がございます。最初の相続の際の相続税の税務申告書で是非ご確認いただき、この制度を活用できる場合には、手間もかかりませんので忘れずに適用していただければと思います。