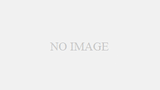各相続人の間で遺産分割協議がまとまると相続する財産が確定します。確定後、相続税の支払いと、相続財産の名義変更などの相続手続きを行い、実際に財産が相続されるという流れになってくると思います。
目次
1.預貯金の一般的な相続手続きの流れ
相続した預貯金を預け入れている金融機関の支店に行き、相続手続きをしたい旨を申し出ます。一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。
(1)ゆうちょ銀行の場合
①相続確認表の提出
記載例を参考にして相続確認表(ゆうちょ銀行、郵便局で取得し、相続人全員の署名・実印を押印します。)を提出すると後日、貯金事務センターより相続手続に関するご案内が届きます。この案内に基づ相続手続きに必要な書類を準備します。
②相続手続きに必要な書類
●被相続人(亡くなられた方)様の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本の原本→市町村役場に出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要である旨を伝え入手します。
●相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
●相続人全員の戸籍謄本
●遺言(存在していれば)
●遺産分割協議書(遺産分割協議を行い作成していれば)
●貯金等相続手続き請求書(名義書換請求書兼支払請求書)
●手続きされる方の本人確認書類(運転免許証等)
③必要書類の提出、郵送
相続確認表を提出したゆうちょ銀行、郵便局に必要書類と貯金事務センターから郵送されてくる書類に同封されている返信用封筒を持参し、窓口で必要書類の確認をしてから、貯金事務センターに郵送します。これらはゆうちょ銀行、郵便局の窓口で対応していただけます。
④通常貯金への入金
相続した貯金等の払戻金が代表相続人の方の通常貯金へ入金されます。現金による受取の場合は、払戻証書が貯金事務センターから郵送されてきますので、その証書を窓口に持参(本人確認書類、印鑑を持参)し、現金を受け取ります。
(2)その他の金融機関の場合
2.法定相続情報証明制度の活用
3.不動産の登記
土地や建物を相続した場合には不動産登記を行いますが、登記の際に必要となる一般的な書類は以下のとおりとなります。
・被相続人様の出生から死亡までの除籍謄本等
・被相続人様の住民票の除票
・相続人様全員の戸籍謄本
・相続人される方の住民票
・登記する年度の不動産の評価証明書
・相続する物件の登記簿謄本
・遺産分割協議書(法定相続以外の場合、法定相続人様全員の印鑑証明書付のもの)
・遺言(遺言により相続した場合)
・相続登記申請書
・相続関係説明図
※すべて原本が必要となります。
※法定相続情報証明制度を活用すると、被相続人様の出生から死亡までの除籍謄本等、被相続人様の住民票の除票など、法定相続情報一覧図で内容が確認できるものは、法定相続情報(原本)を提出することによりそれらの書類を省略することが可能となります。
登記に係る主な費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士報酬(4万円~6万円程度)となります。