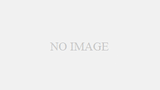相続した財産の手続きが完了すると、正式に相続人の財産となります。相続後は、資産などの構成内容が大きく変化するため、相続する前と後の財産を合計し、資産・負債の現状を確認しておくと資産管理上有用なものとなり、その後の資産形成にも繋がってくることになると思います。
そこで今回は、相続手続き後の資産管理の手順についてまとめてみます。
目次
手順1)相続財産の洗い出し、名義変更、税金の納付の確認。
お亡くなりになると10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をし、税金を納めることになります。その相続税の申告後、お手元には申告書の控えが保管されていると思います。その申告書を見ると相続した資産・負債の内容が記載されております。
その申告書を活用してご自身が相続した資産・負債を洗い出し、その一覧表となる財産目録を作成します。その際には財産目録に記載されている資産、負債のすべてについて名義変更が完了しているか、また相続税の納付が完了しているかどうかも併せてチェックします。
上記のとおり、相続した資産・負債の財産目録を作成し、名義変更、相続税の支払いが完了しているかどうかを確認していきます。相続後時間が経過すると、相続財産の増減が大きくなることもありますので、できるだけ速やかに行うことをお勧め致します。
手順2)相続以前に保有していた資産・負債の確認。
手順1の財産目録を作成した時点での、相続以前から保有していた資産・負債の財産目録の一覧表を作成します。
これは相続する前のご自身の資産・負債内容を整理するために用います。また相続前に特に資産負債の管理を全くしていなかった場合には、今までのご自身の資産などの棚卸しをするという意味でこの財産目録の作成を行っていきます。
手順3) 相続前と後の財産目録の合算。
手順1と2により作成した財産目録を合算して、現時点での資産・負債の現状を把握します。この財産目録を活用し個人のバランスシートの作成を行っていきます。
このバランスシートを作成することにより相続後の資産・負債の全体像が一覧表で確認できるようになります。
資産管理の第一歩目として、まずは相続後の個人のバランスシートを作成し、現状の資産・負債の現状の把握を行っていきます。
手順4)月別のキャッシュ・フロー表の作成。
財産目録を作成した後の1年間のキャッシュ・フロー表を月別で作成していきます。その際、賃貸用不動産などを相続し、新たに収支が増える場合には、それらの収支の影響を加味して作成します。
このキャッシュ・フロー表を作成することにより、相続によりお金の動きがどのように変化したのかを確認できるようになります。
また新たに所得が発生することになる場合には、税務申告にも影響する可能性がござますので、相続申告の際に税理士に事前に確認を行っていただければと思います。
まとめ
相続後は資産などの構成内容、キャッシュ・フローの内容が大きく変化する可能性がございます。上記手順に沿ってその影響の有無を具体的な数字でご確認いただくと、相続後の資産管理がより楽に行っていけるようになると思います。
その際には資産設計の再構築が必要になるかどうかを併せてお考えいただくと、今後の資産管理とともに、将来の資産形成をより効果的に行っていけるものと思います。