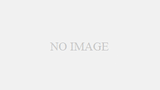2017年1月より加入対象者が拡大され利用機会が増えた、税金負担を軽減して資産形成(個人)が可能となるiDeCo(個人型確定拠出年金)について、加入する前に最低限チェックするルールなどについて今回は見ていきたいと思います。
目次
1.登場する人物
主な登場人物は以下の4名です。
1)加入者:年金資産を形成する本人です。資産形成のための掛金を支払う人です(掛金の支払いが完了し、これまでの資産運用だけを行っている人は運用指図者と呼ばれます。)。
2)窓口、管理者:申し込み手続きや資産形成する商品を提示するなど、加入者と国民年金基金連合会を結びつける総合的な窓口となる人です。証券会社、保険会社、銀行などのことで「運営管理機関」と呼ばれます。
3)主体となり実務を行う人:加入資格、掛金限度額の確認や個人資産の管理など実際の実務を行う人のことで「国民年金基金連合会」と呼ばれます。
4)掛金を引き落とす金融機関:個人が掛金を支払う方法は原則、加入者の預金などから口座振替により行っていきます。そのため、掛金を引き落とす金融機関が登場します。
2.基本的なルール
ルール1:原則20歳以上60歳未満の人は誰でも加入することができます。
ルール2:掛金の支払いは60歳までで、原則60歳まで、資産の途中換金、解約ができません。資産を引き出すことができません。
ルール3:資産を運用する商品は加入者が選択します。その運用結果により資産が減少することがあります。
ルール4:運営管理機関、国民年金基金連合会などへの手数料がかかります。
ルール5:掛金は月額5,000円以上、1,000円刻みで決められています。以下の主な区分による限度額があります。
①自営業【第1号被保険者】:年額816,000円(月額68,000円)
②サラリーマン1【第2被保険者】:年額276,000円(月額23,000円)
※勤務先の会社に企業年金がない場合。
③サラリーマン2【第2被保険者】:年額240,000円(月額20,000円)
※勤務先で企業型確定拠出年金のみに加入している場合。
④専業主婦(夫)など【第3号被保険者】:年額276,000円(月額23,000円)
ルール6:年金資産の受け取りは、原則60歳~70歳までの任意のタイミングで年金か一時金で受け取けとることになります。なおこの受け取る権利は、税金等の滞納の場合を除き、差し押さえをすることができず、受給開始まで保護されます。
3.メリット
メリット1:加入者(個人)が支払う掛金は全額所得控除することができます。そのため、個人の所得税、住民税の課税所得がその分減少し、その結果所得税、住民税の節税となります。
メリット2:資産運用の際に利益が発生する場合、その運用益に対して税金はかかりません。
メリット3:運用した資産を受け取る際にも税制の優遇措置があり節税となります。
・年金で受け取る場合:公的年金等控除により、課税所得が減少されます。
・一時金で受け取る場合:退職所得控除により、課税所得が減少されます。
メリット4:個人資産の持ち運びが可能です。転職や離職した場合でも、手続きを行うことにより解約することなく課税されず、継続して資産形成を行っていくことができます。
4.まとめ
以上のとおり、iDeCoに加入する前に最低限に確認するルールなどについて見てきました。iDeCoは、原則20歳~60歳未満の方であれば誰でも加入でき、5,000円の掛金から始められる身近な制度であるといえます。
しかし、運用している資産を原則60歳まで引き出すことができずに拘束されてしまいますので、無理のない掛金で長期間にわたって資産形成を行う場合には、メリットのある制度であると思います。
将来の年金対策としてiDeCoを活用する場合には、掛金の限度額はそれほど大きな金額ではないので、なるべく早めに加入し、長期間運用することによって、その効果は高まってくるものだと思います。
掛金は年1回変更することができますので、iDeCoに加入する前にはそのルールなどを事前に確認し、制度内容を理解されてから、個人資産形成の1つの手段としてお考えになられるとよろしいかと思います。